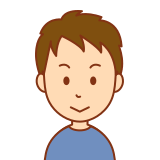
情景描写が大事ってよく聞くけれど、結局どういうものなのかよくわかりません…
今回の記事では、情景描写がどういうものなのか、初心者にもわかりやすく解説しています。小説を書く上での役割や物語への効果についても解説しているので、「意味がわからない」と書く手が止まってしまっている人はぜひ参考にしてください。
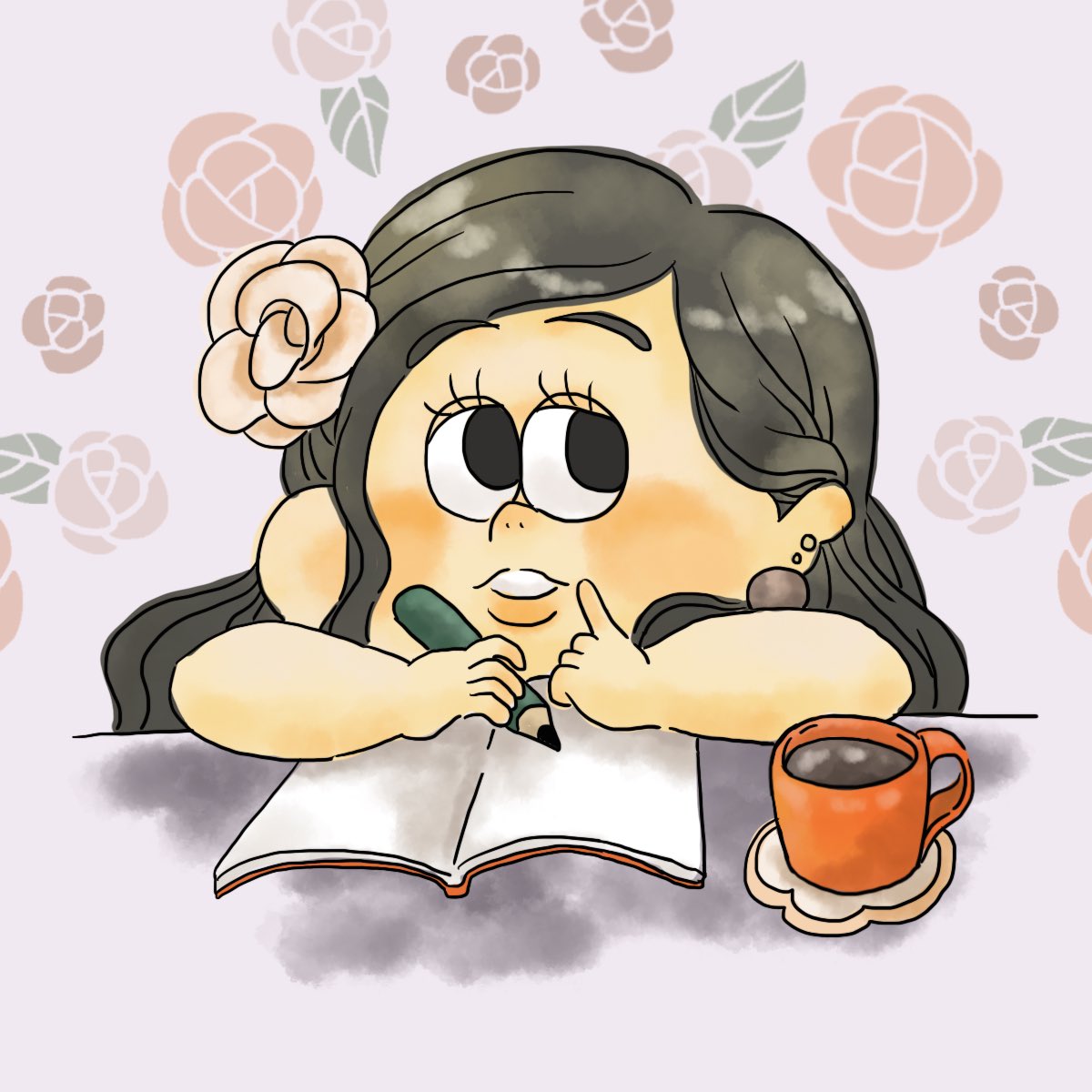
作品を際立たせられる使い方のコツも紹介しています!
そもそも情景描写って何?
情景描写とは、登場人物の周囲の風景や空気感、音、匂いなどを通して、その場の“雰囲気”や“心情”を読者に伝える技法のことです。
「春の風がカーテンをやさしく揺らしていた」
例えば、上記の文章からは季節が春であること、カーテンの揺らぎが際立つほどの静けさ・春の風と愛まった温かさが感じられます。
この場面が学校の教室、部室などの場合、なんだかこれから和やかな日常が進んでいきそうな気がしませんか?
情景描写の役割と物語への効果
情景描写を描くことで、まるで読者がその世界に実際にいるように感じさせることができます。その空間に響いている音・匂い・空間の狭さなど。
文章を読むことで、実際に頭の中でその場面を見ているような、そこにいるように感じさせる効果があります。
読者を世界に引き込む
情景描写を描くことで、読者は文章を読んでいるだけで頭の中で自然に景色を浮かべられるようになります。光の明るさ、空気の湿り気、足音の響き――そうした細部を描くことで、物語を立体的に感じさせられます。
「駅のホームに冷たい風が吹き抜けた。夕陽に照らされた線路が、どこまでも赤く光っている。」
このように具体的な描写を入れることで、まるで映画のワンシーンを見るように、世界観を“体感”できるのです。
登場人物の感情を反映させる
情景は、登場人物の心情を「見せる」役割も果たします。
「机の上のコーヒーは、もうすっかり冷めていた」
この一文には、「待ち続けている」「諦めかけている」など、直接書かれていない感情が感じられます。読者は、描かれた風景を通して登場人物の心を感じられるでしょう。
反対に、同じコーヒーを題材にしても「温かいコーヒーが僕の心を解きほぐしてくれるようだ」と書けば、「癒されている」「ホッとした時間を過ごしている」ということがわかるでしょう。
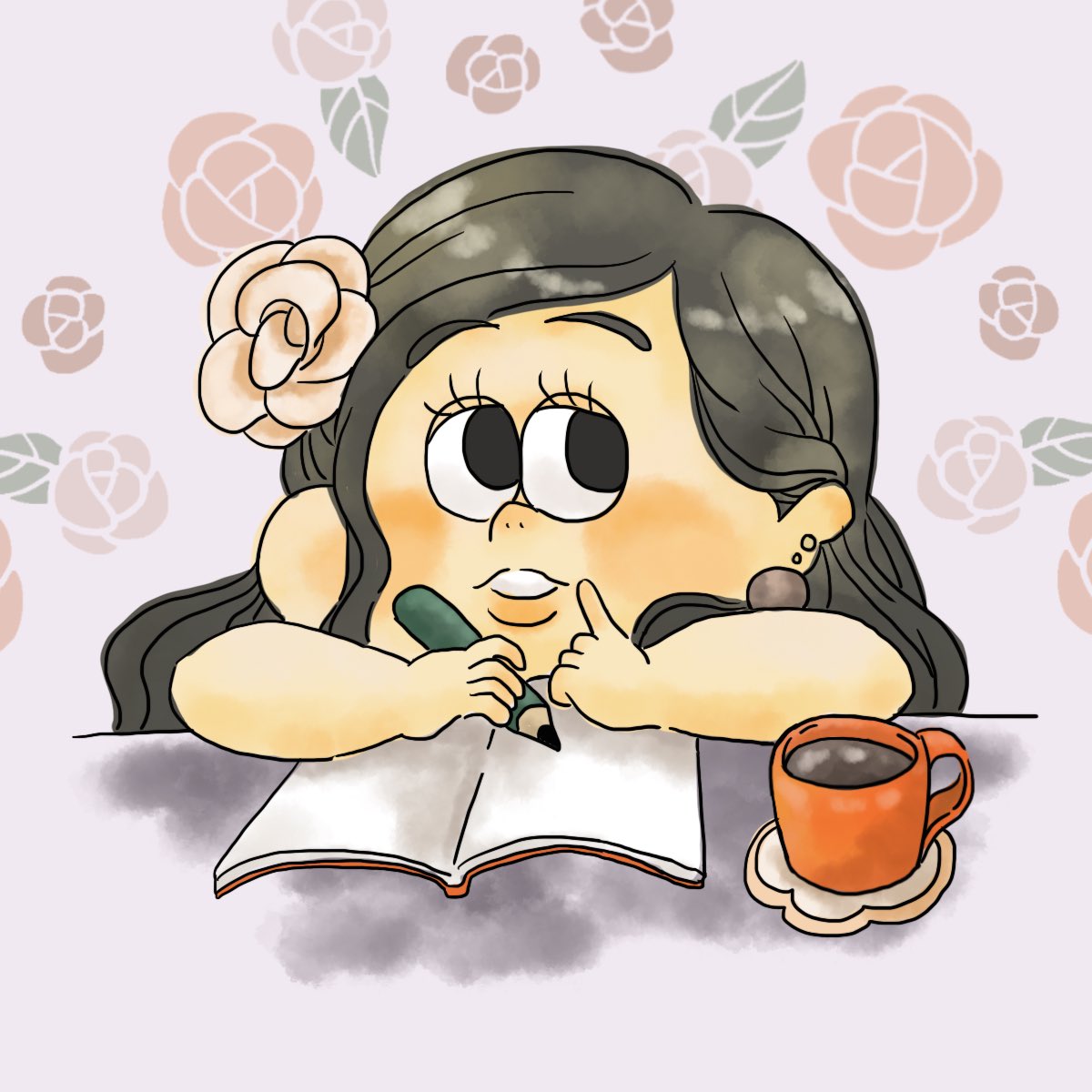
このように、情景描写には心情を直接描かずに“暗示”させる効果があります!
また、人間の心はその時々の感情によって世界の見え方が変わります。例えば、同じ「雨の夜」一つとっても、登場人物の心情によって見え方は大きく異なります。
つまり、情景描写は登場人物の心を映し出す鏡なのです。
雰囲気づくり
文章の雰囲気は、登場人物の目線や風景の描き方で決まります。
風景や光、色彩、天候の描写を通じて、文章の「色味」が自然に決まります。
また、情景描写は描写の長さや細かさを変えることで、小説のリズムをコントロールできます。展開を早くしたい時、反対に重々しい空気を感じさせたいなど、文章のテンポを自由に変えられます。
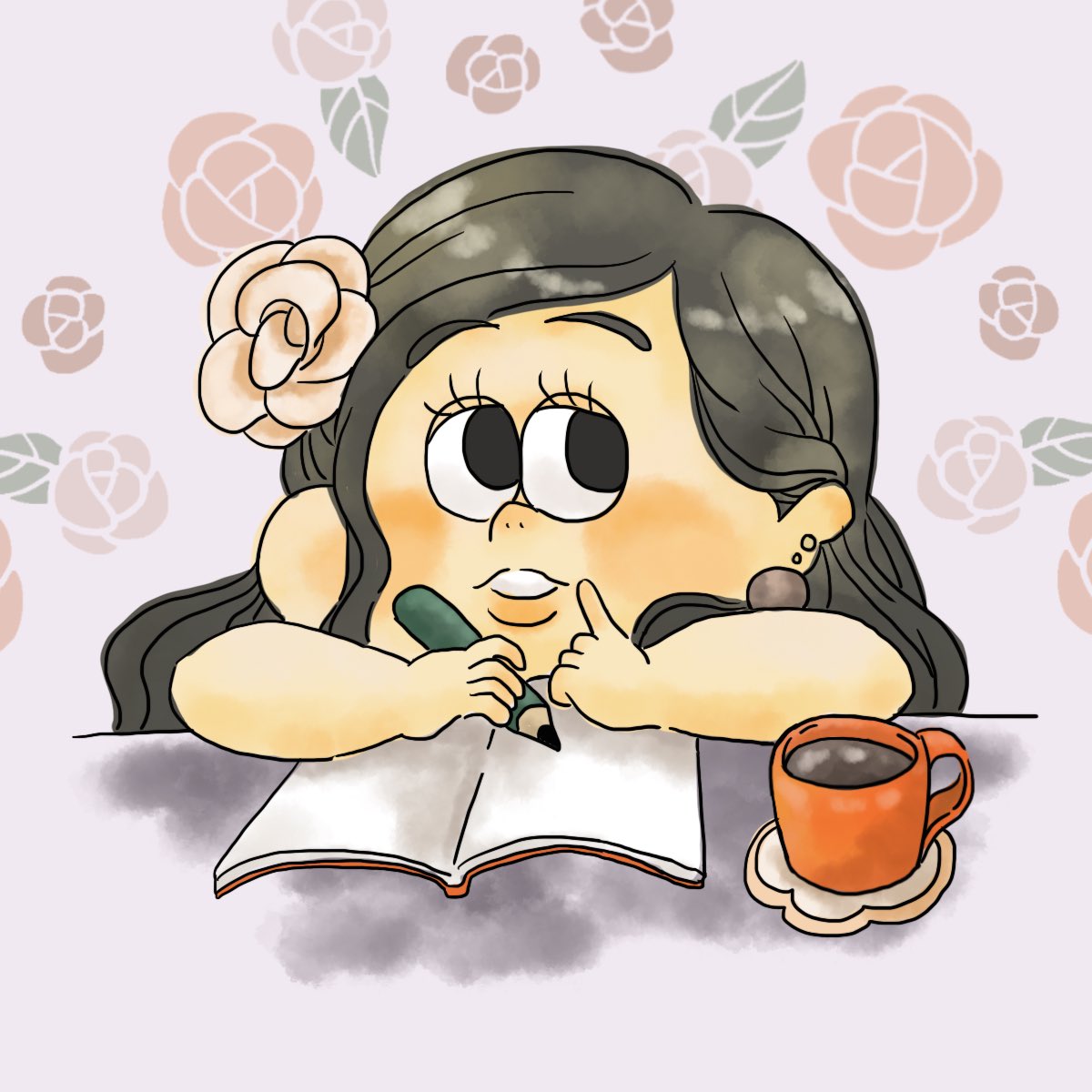
どこまで描くのが良いの?と悩む時は、どのようなテンポで読んで欲しいかを考えましょう!
情景描写を効果的に使うコツ
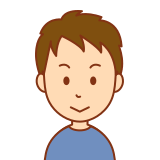
情景描写の意味はわかりましたが、使い方がわかりません!
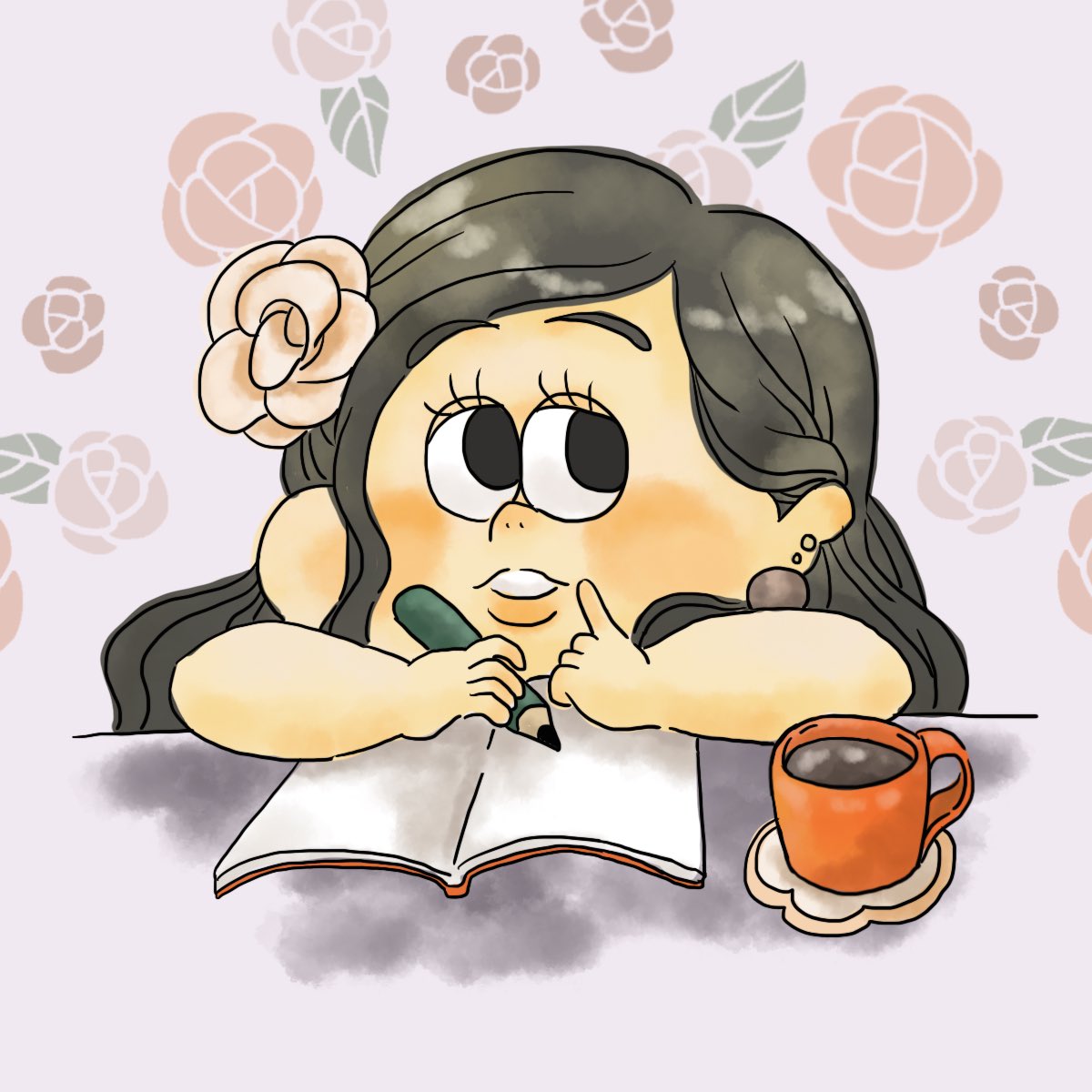
それでは、実際に情景描写を使う時のコツを紹介します!
情景描写の描き方がわからない人は、ぜひ参考にしてください。効果的に使えるようになることで、今よりも読者を没入させられる作品が作れるようになりますよ!
1. 五感を使って描く
読者を世界に引き込むには、「目に見えるもの」だけでは足りません。情景描写を効果的に使うためには、視覚だけでなく五感で捉えると、描写が一気にリアルになります。
| 感覚 | 描写例 |
|---|---|
| 視覚(見る) | 灰色の雲が低く垂れ込めている |
| 聴覚(聞く) | 遠くで電車の音がかすかに響いた |
| 嗅覚(匂う) | 焙煎した豆の香りがふわりと漂う |
| 触覚(触れる) | 冷たい風が頬を刺した |
| 味覚(味わう) | コーヒーの苦味が口の中に残った |
特に嗅覚・触覚の描写は印象に残りやすく、場面に深みを出す効果があります。描写をする時は、「この場面で読者にどんな気持ちを感じてほしいか?」を考えると描きやすいです。
2. 心情とリンクさせる
「情景描写をどのように描けばいいのかわからない!」という時は、登場人物の心情とリンクさせましょう。感情と結びつけることで、「ただ風景を説明しただけ」といった問題をなくせます。
登場人物の感情をそのまま書く代わりに情景に重ねることで、読者に心の内を想像させられます。「僕は悲しい」「前向きになれそうだ」といった直接的な言葉を書くよりも、物語に深みを持たせられます。
3. 対比を意識する
情景描写を書く際、対比を意識すると読者に強い印象を与えられます。例えば、明るい情景から一転して暗い描写に変わると、感情の起伏が際立たせられます。
「さっきまで笑い声で満ちていた部屋に、時計の針の音だけが残った」
登場人物たちが楽しく盛り上がっている後に、この描写を入れることで主人公の寂しさや孤独感を強調できます。
対比を意識することで、心情やテーマをより際立たせられます。
- 明るさと暗さ
- 静けさと音
- 温かさと冷たさ
- 人の感情と風景のギャップ
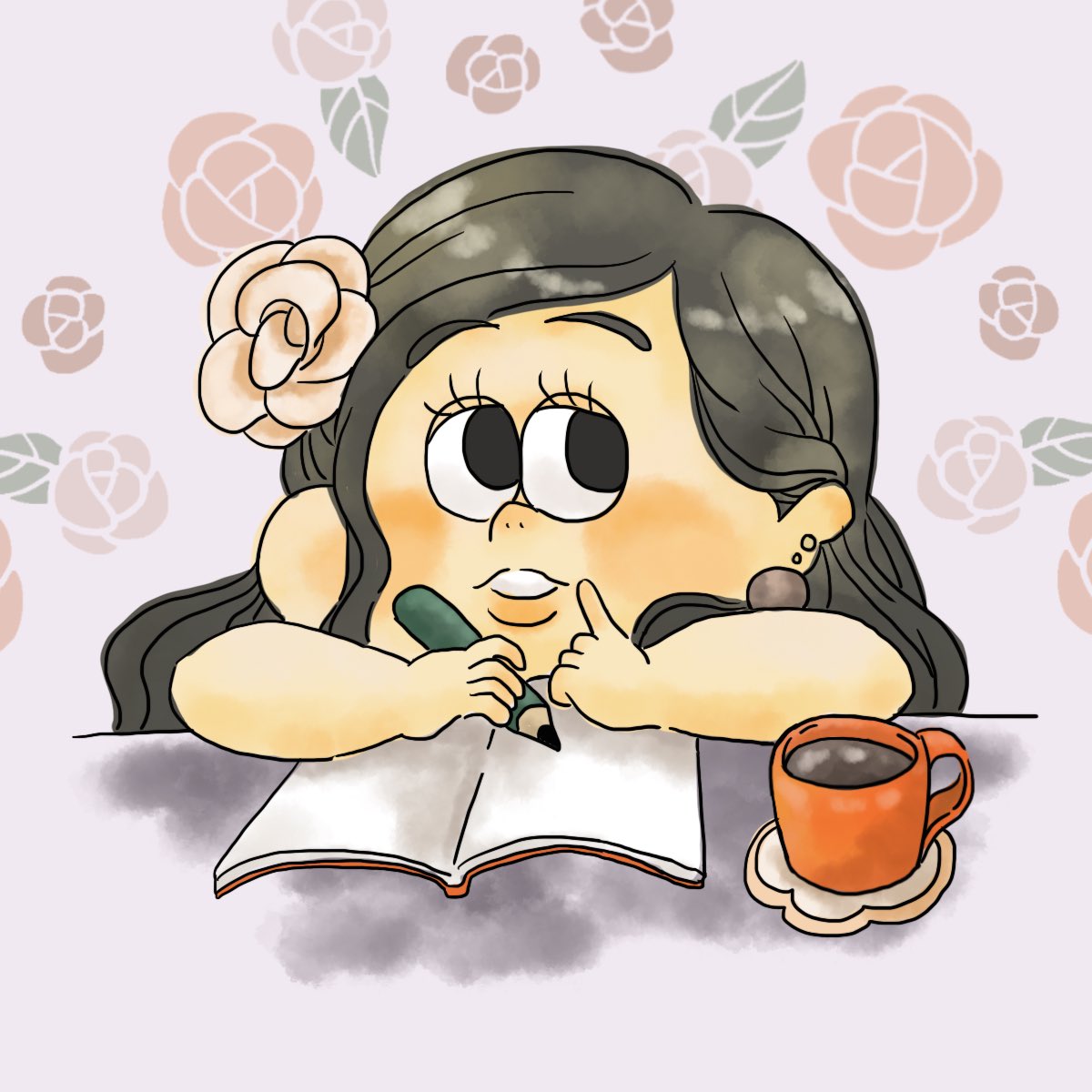
対比を感じると、その場面がより強く印象に残ります!
つまり、感情を強く伝えるためには、感情の“反対側”を少し見せることが効果的なのです。
情景描写が難しいと感じる理由と上達のヒント
情景描写が難しいと感じるのは、「どこまで描けば良いのかわからない」「判断基準が難しい」からです。
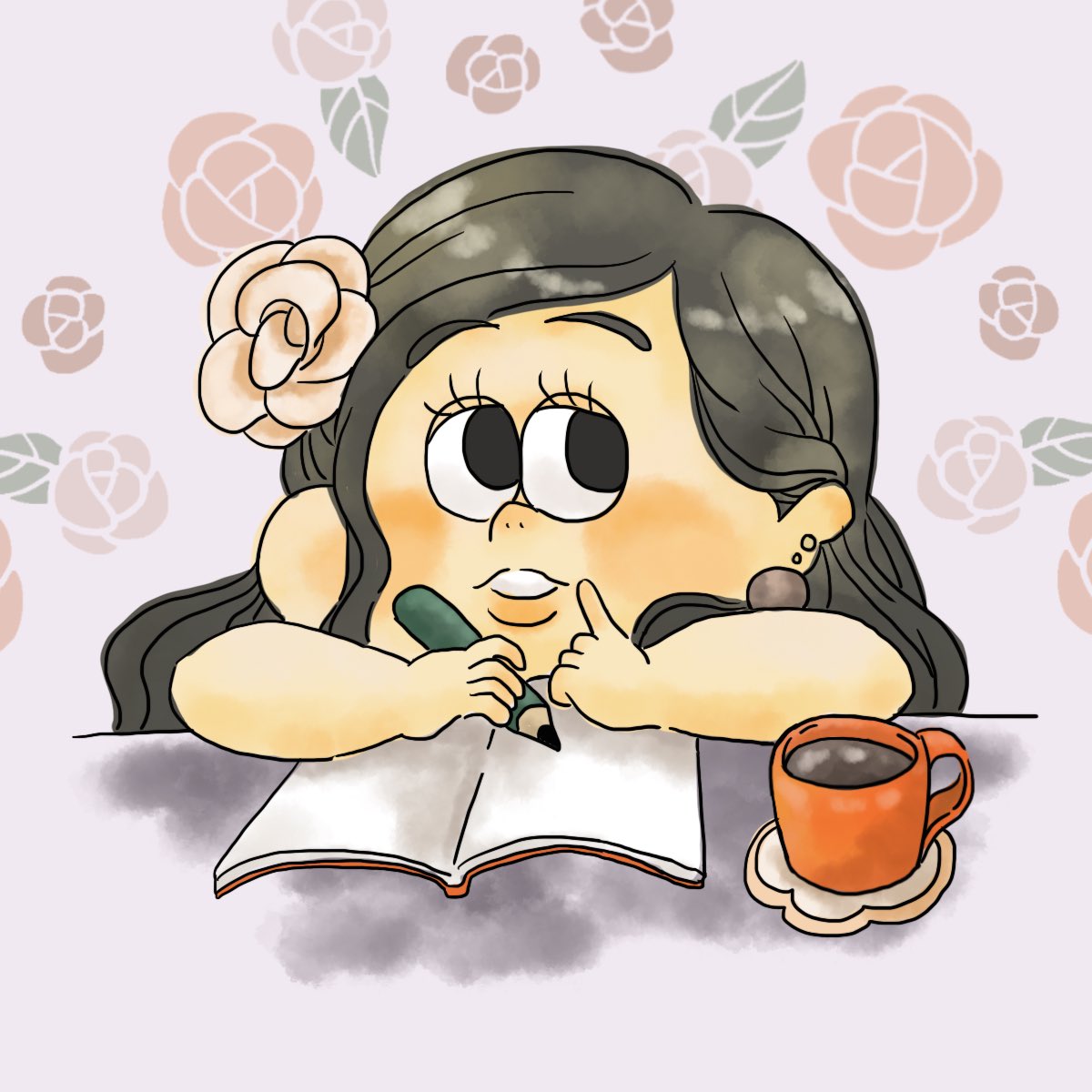
描きすぎても描かなさすぎても、中途半端になるのが難しいところです。
情景描写の量を考える時は、「その描写で何を伝えたいか?」「読者に何を感じてほしいか?」を基準に考えましょう。
描くことが目的になるのではなく、描く理由を明確にすると読者の想像を助ける描写が描けるようになりますよ。
コツは「風景を見せるの」ではなく「感じさせる」ことです。実際の景色を描くのではなく、そこにある「空気感」や「温度」を伝える意識で書くと自然になります。
前章で書いた3つのコツを意識して書いていくと、自然と読者に感じさせられる描写が描けるようになります。
まとめ|情景描写は“感情を映す鏡”
情景描写は、風景を説明するためではなく、登場人物の感情や物語の空気・テンポ・雰囲気を伝えるためのものです。「読者に何を感じさせたいか」を意識することで、自然と印象に残る描写が作れるようになります。
描くのが難しい…という方は、まずは登場人物の心情と重ねて描いてみてください。書きやすい描写や、「ここぞ!」というポイントを描けるようになるだけで、物語の雰囲気を大きく変えられますよ。
以下の記事も併せてご覧ください。
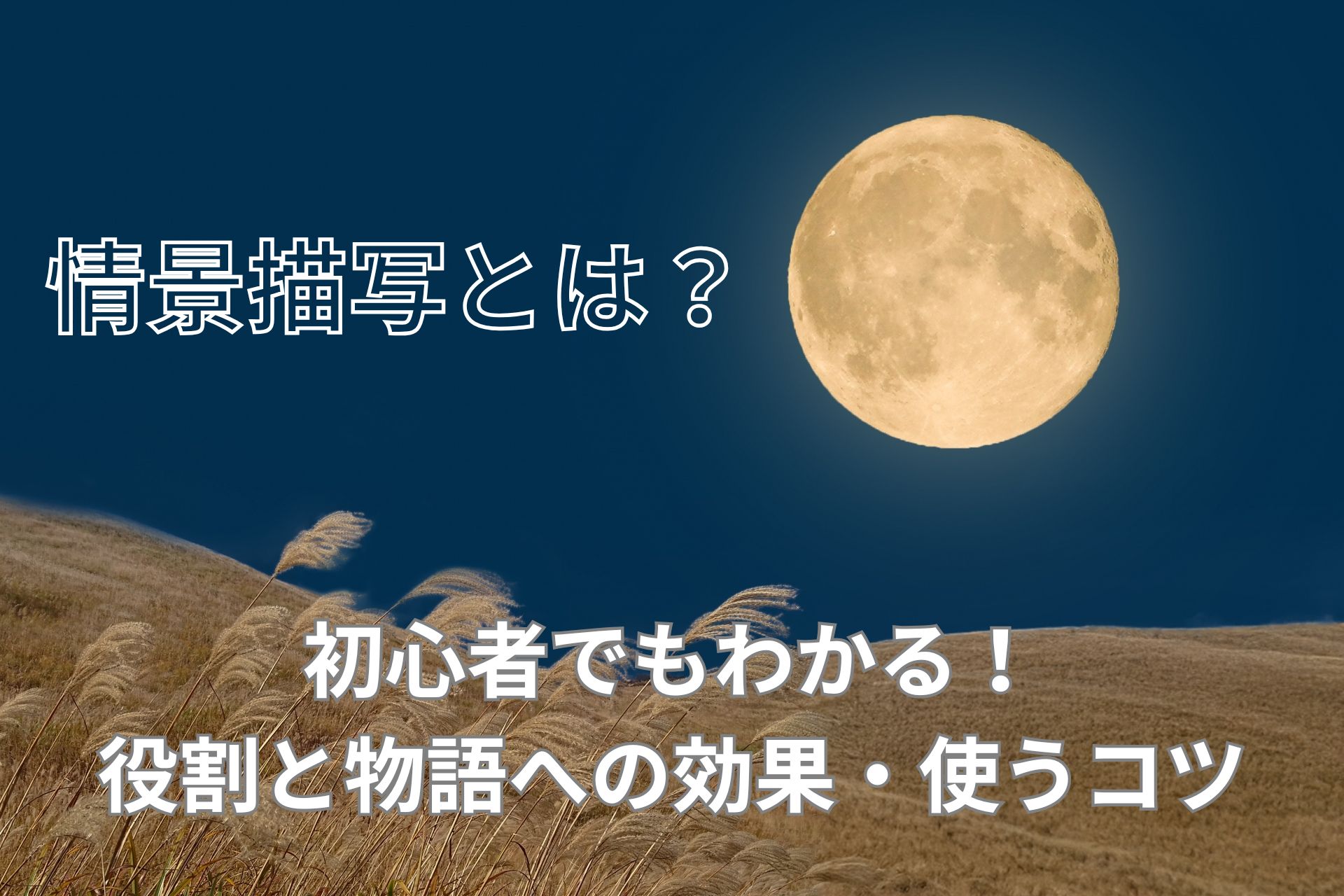



コメント